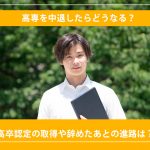不登校は大学受験で不利?進学を目指すなら高卒認定試験がおすすめ
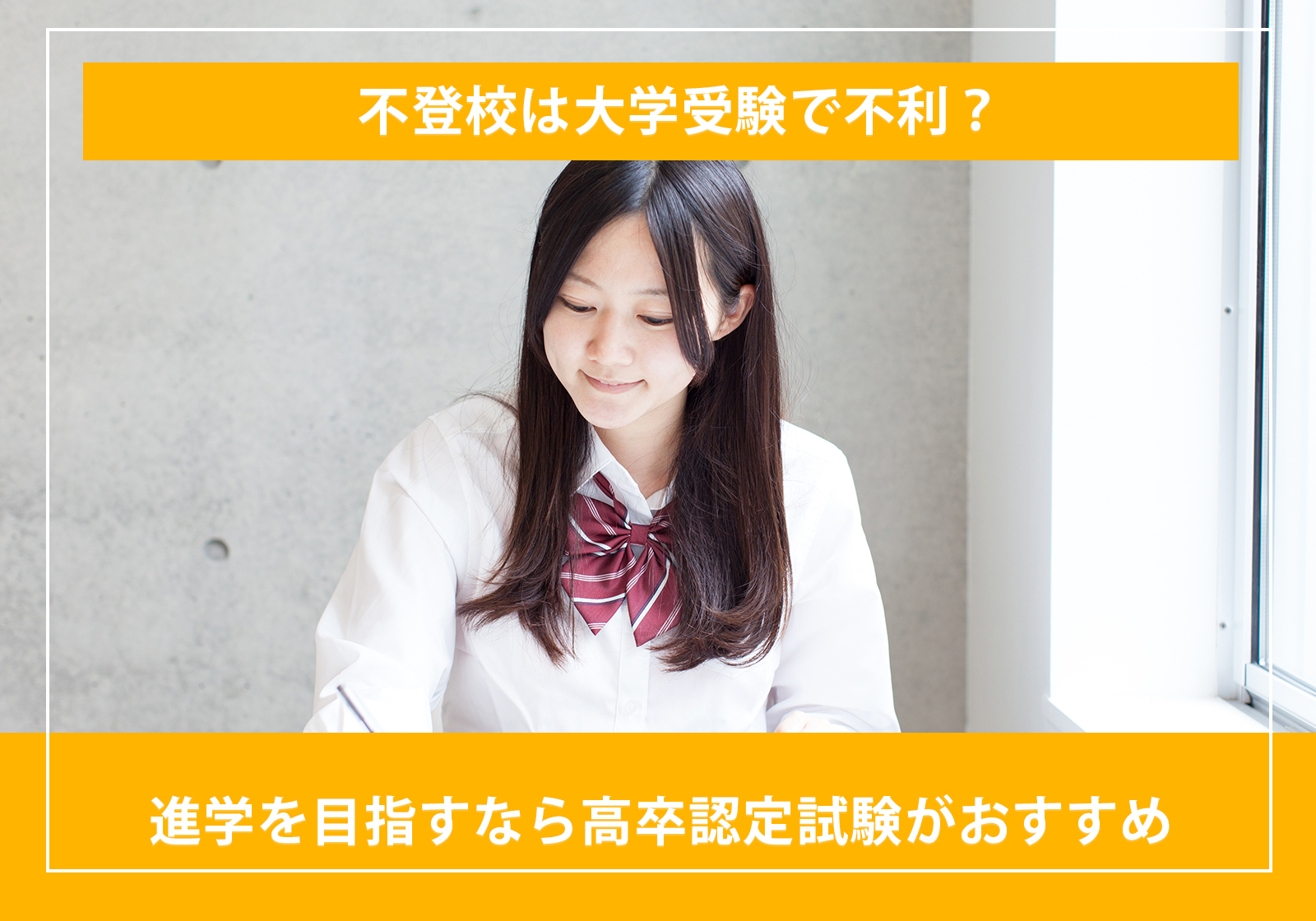
不登校を経験した方やその家族にとって、「不登校だと大学受験で不利になるか」気になるでしょう。なかには、大学進学をあきらめてしまう方もいるかもしれません。しかし、不登校の経験があっても大学受験の壁を乗り越え、合格することは十分に可能です。
この記事では、不登校経験者が大学受験で「不利」だと感じてしまう理由を明確にし、不安を解消するための具体的な方法を紹介します。
不登校が大学受験で「不利」と感じる理由

不登校が大学受験で不利だと感じられる理由は、おもに2つあります。理由を理解しておくと、自分に合った対策を考えやすくなります。
内申点の壁
多くの大学では、一般入試(大学入学共通テストと個別試験)に加えて、高校での成績や出席状況が記載された「調査書」、いわゆる内申点を合否の判断材料にしています。特に、推薦入試や総合型選抜(旧AO入試)では、内申点が大きな役割を果たします。
不登校の期間が長いと、授業の出席日数や定期テストの受験、提出物の数が不足しやすく、その結果、内申点が低く評価される傾向があります。この点は、推薦入試や総合型選抜を目指す受験生にとって大きなハードルとなるでしょう。
ただし、内申点が重視されない、あるいは評価の割合が低い入試方法もあります。そのため、内申点が低いという理由だけで大学進学をあきらめる必要はありません。
学力面の遅れ
長い間学校に通えなかったことで、学習範囲を十分にカバーできていないのではという不安は、不登校を経験した方にとって大きな悩みの一つです。高校の授業は進むスピードが速く、一度つまずくと自力で取り戻すのは簡単ではありません。特に、主要科目の基礎が不足していると、大学入試で求められる応用力を身に付けるまでに時間がかかることがあります。
そのため、「不登校だと大学受験に失敗するのではないか」「大学に入っても授業についていけないのではないか」と自信をなくす方もいます。しかし、この不安は学習方法を工夫すれば、解消することができます。
不登校でも大学受験に挑戦できる3つの選択肢

不登校による「内申点の壁」や「学力の遅れ」は、大きな不安につながりますが、それだけで大学進学をあきらめる必要はありません。実際に、不登校を経験しながら大学受験を突破した方は数多くいます。大切なのは、自分に合った方法を見つけ、一つずつ着実に取り組むことです。
ここからは、不登校を経験した方でも大学受験に挑戦できる、3つの代表的な選択肢を紹介します。
総合型選抜(旧AO入試)を受ける
総合型選抜は、学力試験の結果だけでなく、面接や小論文、活動実績、志望理由書などを総合的に評価する入試方式です。大学は、求める人物像と受験生の個性や可能性が合っているかを重視します。
この入試方式では、不登校の経験が必ずしも不利になるわけではありません。むしろ、不登校の期間に独学で取り組んだこと(例:プログラミング、語学学習、資格取得など)や、ボランティア・芸術活動を通じて得た経験を前向きに語れれば、大きなアピールポイントになるでしょう。
通信制高校へ転入・編入する
現在高校に在籍していない、あるいは通えなくなってしまった場合は、「通信制高校への転入・編入」が有力な選択肢になります。
通信制高校では、レポート提出やスクーリング(対面授業)を通じて単位を取得し、卒業を目指します。自分の生活リズムや体調に合わせて学習できるため、不登校を経験した方にとって心理的な負担が少なく、無理なく高校卒業資格を得ることが可能です。
通信制高校を卒業すれば、一般的な高校卒業生と同じ資格を得られるため、さまざまな入試方式で大学受験に挑戦できます。
さらに、多くの通信制高校は進路相談や学習サポートも充実しており、大学進学に向けて手厚い支援を受けられる点も大きなメリットです。自分のペースを大切にしながら高校生活を送り、大学進学という次のステップへつなげられます。
高卒認定試験を受ける
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)は、高校を卒業していない方でも「高校卒業と同じ学力がある」と認められる国家試験です。合格すると、大学や短大、専門学校の受験資格を得られます。
高卒認定試験は、内申点の影響を一切受けないことが大きなメリットです。不登校で高校に通えていない方にとっても、大学進学への道を切り開く手段となります。
さらに、自分のペースで学習でき、一度合格した科目は翌年以降も有効です。計画的に勉強を進めれば、着実に合格を目指せます。
不登校経験者にとっての高卒認定試験の強み

大学進学を目指す不登校経験者にとって、高卒認定試験は現実的で心強い選択肢です。ここからは、その強みと学習の進め方について、さらに詳しく見ていきましょう。
高卒認定試験のメリット
高卒認定の最大のメリットは、不登校で高校を卒業できなかった場合でも、この試験に合格すれば大学受験の資格を得られることです。出席日数や成績を気にする必要はなく、試験の点数だけで合否が決まります。
さらに、最短で半年~1年ほどの学習で合格を目指せるため、時間的なロスを最小限に抑えられる点も大きな魅力です。
高校の全日制課程を卒業するよりも、早く大学受験に挑戦できる可能性があります。合格後は、大学入試に向けた勉強に集中できる点もメリットといえるでしょう。
高卒認定試験の学習方法
高卒認定試験は独学でも合格できますが、多くの受験生にとって効率的な学習計画を立てるのは簡単ではありません。特に不登校を経験した方のなかには、「どこから勉強をはじめればよいのかわからない」「一人だとモチベーションが続かない」と悩むケースも少なくありません。
合格を目指すうえで役立つのが、体系的に学べる教材や、質問できる指導者の存在です。自分の学習レベルに合わせたカリキュラムがあり、つまずいたときに相談できる環境が整っていれば、学習を着実に進められます。
例えば、高卒認定試験に特化した学習ができる予備校や塾では、効率的に学習を進められるだけでなく、大学受験を見据えたサポートも受けられます。
高卒認定試験のサポートを行う予備校や塾もある
効率よく高卒認定試験に合格し、その先の大学進学を目指すには、高卒認定に特化した予備校や塾を利用するのが有効です。
例えば、四谷学院の高卒認定コースでは、基礎から丁寧に学べるカリキュラムが用意されています。不登校で学習が途切れてしまった方でも安心して勉強を再開でき、授業では基礎から解説してくれるため、「自分には無理だ」と思っていた科目も克服できる可能性があります。
また、これらの予備校や塾は高卒認定試験対策だけでなく、そのあとの大学受験まで見据えたサポートを行っています。志望校の選び方から入試科目の対策、小論文の書き方、面接練習まで、合格に必要な準備を幅広く支援してくれるのが大きな強みです。
高卒認定に合格して終わりではなく、大学進学という次の目標まで視野に入れて取り組めるため、一人で悩まず前進できます。学習のモチベーションを維持し、不安を解消するうえでも心強い存在となるでしょう。
不登校者の大学受験でよくある質問

不登校を経験した方が大学受験について抱く疑問は多く、特に「受験で不利になるのか」「進学はできるのか」「内申点はどのように影響するのか」といった点がよく挙げられます。
ここでは、そうした疑問に対する具体的な答えについて見ていきましょう。
不登校だと大学受験に不利になる?
長期間学校に通えなかったことで授業や提出物が遅れたり、定期テストの成績が思うように取れなかったりすると、推薦入試や総合型選抜での評価に影響する可能性があります。
しかし、不登校の経験が大学進学を阻むわけではありません。総合型選抜や高卒認定試験など、多様な入試方式を活用すれば、不登校を経験していても大学進学は十分に可能です。不利だと感じる点を理解したうえで、それを補う方法を計画的に進めることが大切です。
さらに、不登校の経験は自分を深く見つめ、独自の視点や考え方を育む貴重な時間でもあります。その経験をアピールポイントとして前向きに伝えれば、強みに変えることもできます。
不登校でも大学に進学できる?
高校を卒業していなくても、通信制高校に転入・編入すれば卒業資格を取得でき、大学受験資格を得られます。また、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格することでも、大学や専門学校の受験資格を得られます。
さらに、総合型選抜や面接を重視する入試方式では、不登校の経験を「自分の人生の一部」として前向きに語ることが強みになります。状況に応じた選択肢を組み合わせることで、不登校を経験した方でも大学進学は十分に実現可能です。
不登校だと内申点に影響はある?
不登校の期間があると、内申点にはどうしても影響が出ます。出席日数や提出物、定期テストの成績が評価対象となるため、低くなりやすいからです。しかし、大学入試は多様化しており、内申点が不要な入試も少なくありません。
例えば、一般入試(大学入学共通テスト+個別試験)や高卒認定を利用する場合、内申点は合否に直接関係しません。つまり、「不登校=大学進学できない」わけではなく、自分に合った入試方式を選ぶことが合格への近道になります。
また、予備校や塾を活用して効率的に学力を補えば、内申点以外の部分でしっかりと評価される可能性があります。
まとめ
不登校の経験があると、大学受験は不利に感じるかもしれませんが、内申点や学力の遅れを補う方法はあります。
特に高卒認定試験は、高校を卒業できなかった方にとって大学進学への道を切り拓く制度です。予備校や塾のサポートを活用すれば、効率的に学習を進め、自信を持って大学受験に挑戦できます。
不登校の経験は、決して失敗ではありません。これまでの経験を強みに変え、将来の道を切り開く一歩を踏み出しましょう。